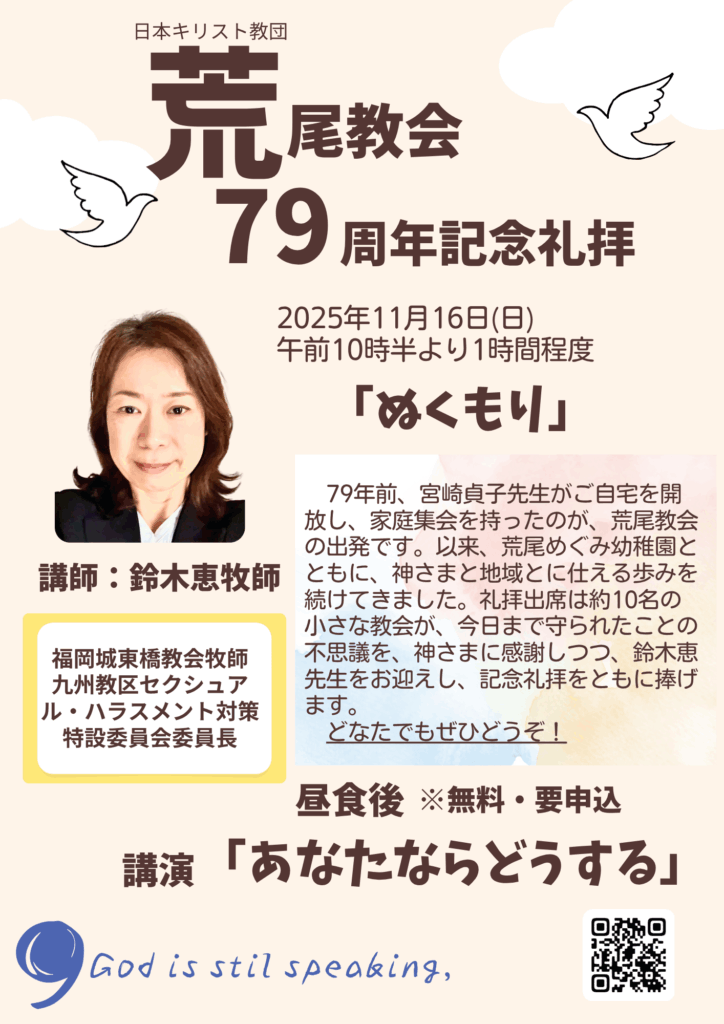教会とはギリシア語でエクレシア(ἐκκλησία)ですが、その原意は「神に呼び集められた者たち」となります。建物ではなく、そのような人々の共同体です。では神に呼ばれること=召命(calling)とは何なのでしょうか?
この問いに答えることは決して自明なことではありません。モーセも神から呼ばれた時に、迷いむしろ断ろうとして言いました。
「わたしは何者でしょう。どうして、ファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。」
神は言われた。 「わたしは必ずあなたと共にいる。このことこそ、わたしがあなたを遣わすしるしである。」 (出エ3:11-12)
つまり、何者であるかは問わないのです。立派な実力や経歴あるいは資産や権力があるから、神は選んだのではないのです。むしろ「貧弱」(申7:7)な者を神は呼ばれるのです。わたし達に与えられているのは、「神我らと共に(インマヌエル)」という「しるし」のみです。
2019年、教区宣教会議が大牟田正山町教会であり、K教師(錦ヶ丘教会)が「牧師の召命」について次のように言われていました。
召命は自己責任ではない。個人的なことではなく、ちゃんと後ろ盾があって初めて召命は成り立つ。地区・家族・教会の祈りやサポート。教師の側も相談していく大切さ。学閥などを越えて協力し合う仲間がいたからやっていけた。
神さまは確かにわたし達一人一人に呼びかけています。しかし、一個人の召命(calling)だけでは倒れてしまいます。神に呼ばれている一人ひとりが祈り支え合う共同体こそが教会(エクレシア)なのです。
2025年も拙い牧師の働きを祈り支えて下さったことを感謝いたします。2026年も、荒尾教会・山鹿教会共々に祈り支え合っていきましょう。(有明海のほとり便り no.442)